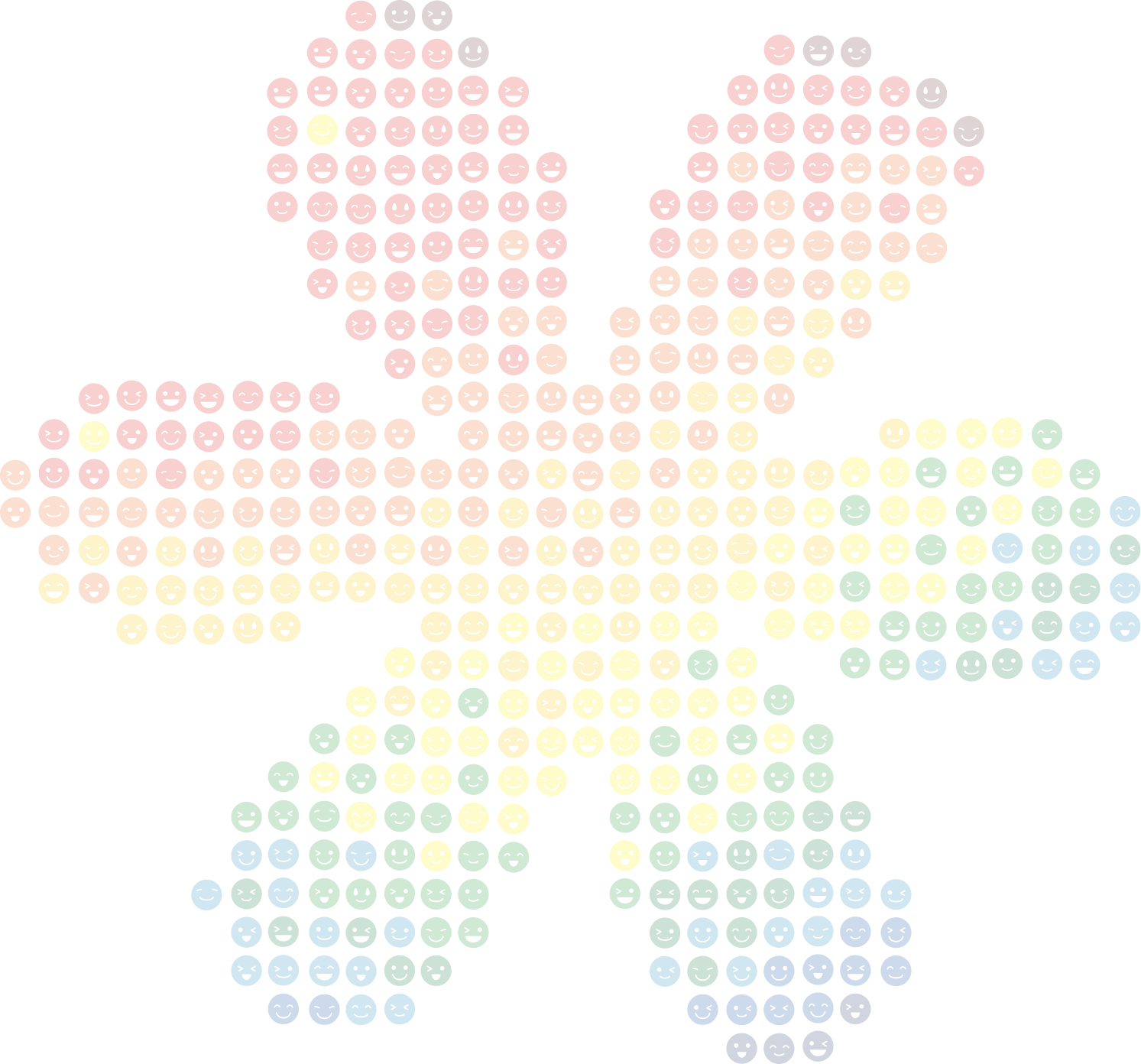社長日誌
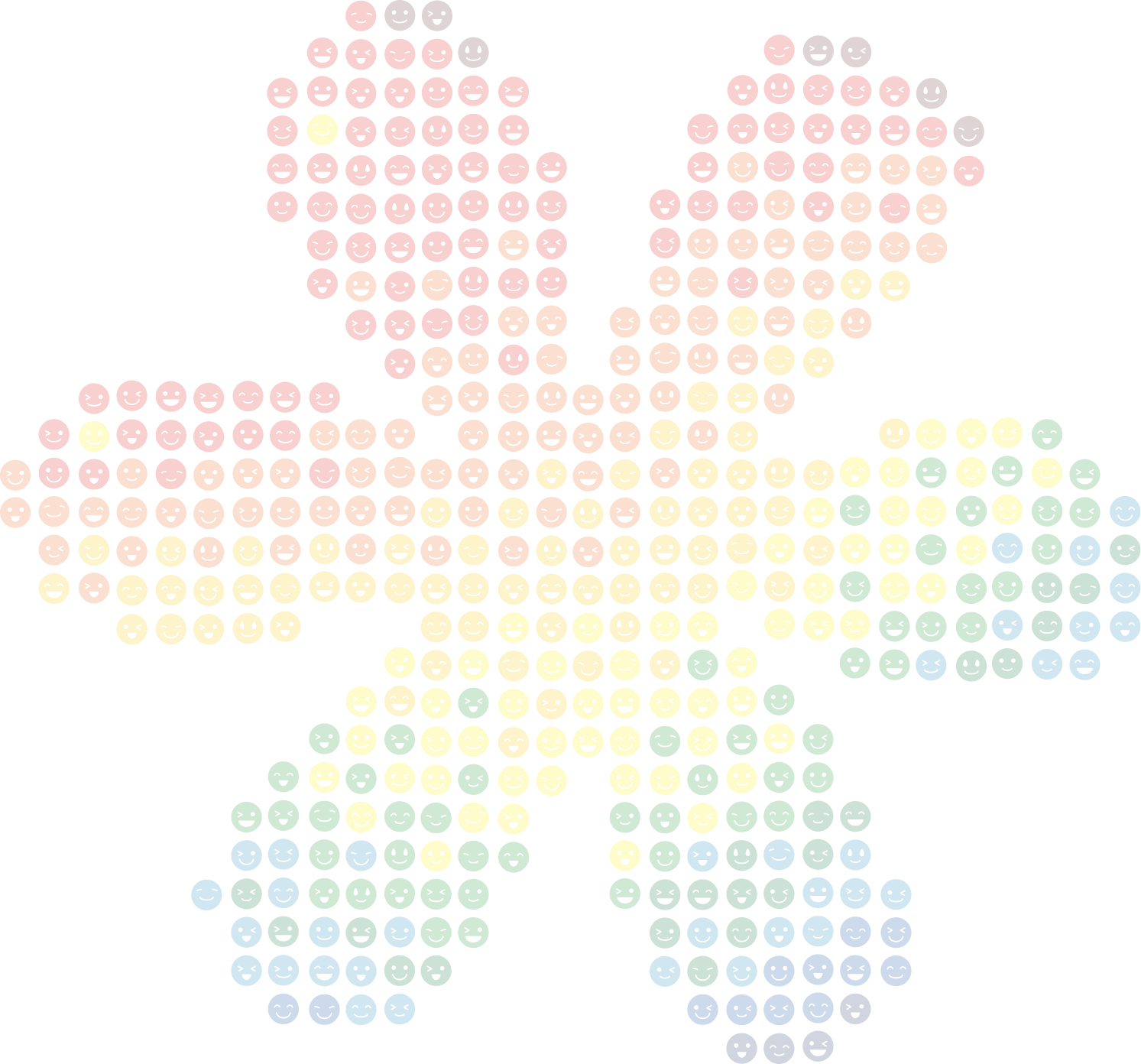
ランジーン×コード
ライトノベルってなんだろうと思っておりましたが、要は私が高校生時代なんかに読んでいた「クラッシャージョー」や「吸血鬼ハンターD」なんかのようなソノラマ文庫や新井素子、氷室冴子が活躍したコバルト文庫のようなジャンルがいつの間にかライトノベルという呼び名になっているようで、和製英語ですが、日本のサブカルチャーの一つとして海外でも定着しているとのことです。
「このライトノベルがすごい!」大賞は宝島社がライトノベルへ力をいれるために創設した賞で、文庫名にもそのまま使われております。
ランジーンコードはこの第1回 大賞受賞作でライトノベルとはいえ構成もしっかりしており、読み応えがあります。
マンガと小説の間を埋めるような分野ですので、人によって好き嫌いはあると思いますが、今後、注目していきたいですね。(*^_^*)
体調不良
先日からの体調不良にもかかわらず、予定通り海外にきております。
しかし、下痢がとまらないので、ホテルから出ることもままならず一人で一日中本を読みながら寝ております。
いったい何をしに来たのかという感じです。(>_<)
名古屋出張
昨日は名古屋へ出張しておりました。
前日から体調が悪くなったのですが、2人の社員と一緒の出張だったので、無理して行きました。
しかし、全身がだるくて、訪問先に到着するとヘロヘロになりながらなんとか仕事をして、車の中ではリアシートでひっくり返るの繰り返しです。
予定通り4軒の取引先で仕事をすませ、帰ってきて計ってみると熱が出ておりました。
やっぱり無理はいけませんね。(>_<)
ジロー
帰国
新幹線
丸山
昨日は次の取引先まで、車で3時間かけて移動し仕事をしました。
仕事を終えると、更に宿泊先の上海までは車で2時間です。
夕食は居酒屋風の和食料理屋の「丸山」へ行きました。
最近は原発事故による放射能問題で、香港の和食料理店が危機的状況だという記事を読んでいたので、こちらは大丈夫なのだろうかと心配をしておりましたが、8時頃には広い店内もいっぱいになっていたようで一安心です。
しかし、日本料理の店によっては、店内に「日本からの食材は使用しておりません」というような張り紙をしているところもあるようで、悲しい限りです。
一日も早く正常に戻ってほしいものです。
ハードスケジュール
昨日は4:30に自宅を出発して、関空から上海へ
ほぼ定刻に到着し、車で目的地へ
昼食は、関空のローソンで買ったおにぎりを車中で
車で高速道路を走ること4時間半
工場で4時~8時まで仕事
8時半頃から食事、初めての取引先なので、いつものように乾杯が始まる。
今回は北寄りなので、白酒での乾杯(42度以上)
工場の総経理とは仲良くなるが、へろへろになる。
食後にマッサージへ行ってホテルに帰ると1:00
そこから仕事を始めたので、現在は2:20
本日は6:00に起床、7:00出発
次の目的地へ向かうが、高速道路をぶっとばして3時間ということです。(^^)
裏技
本日から中国出張ですが、自宅を4:30に出発です。
関西国際空港の駐車場は非常に高いイメージがありますが、実は23時から7時までに入庫すると何日 泊めても1,000円/日なんです。
今回は3泊4日の出張ですので、正規料金は10,000円ですが、4,000円ですんでしまいますので、朝の便に乗るときは、ちょっと早めに出て7時までの入庫を目指します。
しかし、時差の関係もありますので、3:30に起床して、中国で12:00近くの就寝になると、21時間くらい起きている計算になりちょっと辛いものもあります。
経費節減も大変です。(^^)
明日から中国出張
明日から中国へ出張です。
経営指針書の作成も大詰めを迎えておりますので、私が中国へ行くまでと思い、担当者は連日、原稿を依頼に来たり、印刷許可をもらいに来たりと大変でした。
しかし、とうとう本日は最終日で、明日からは不在ですが、どうも予定まで進んでないようで、中国でも確認できるように、できているところまでの見本を持って行くようにと渡されました。
私も中国で昼間は商談して、夜は指針書のチェックというのも大変ですが、時間もないので頑張っていかなければなりませんね。(^^)