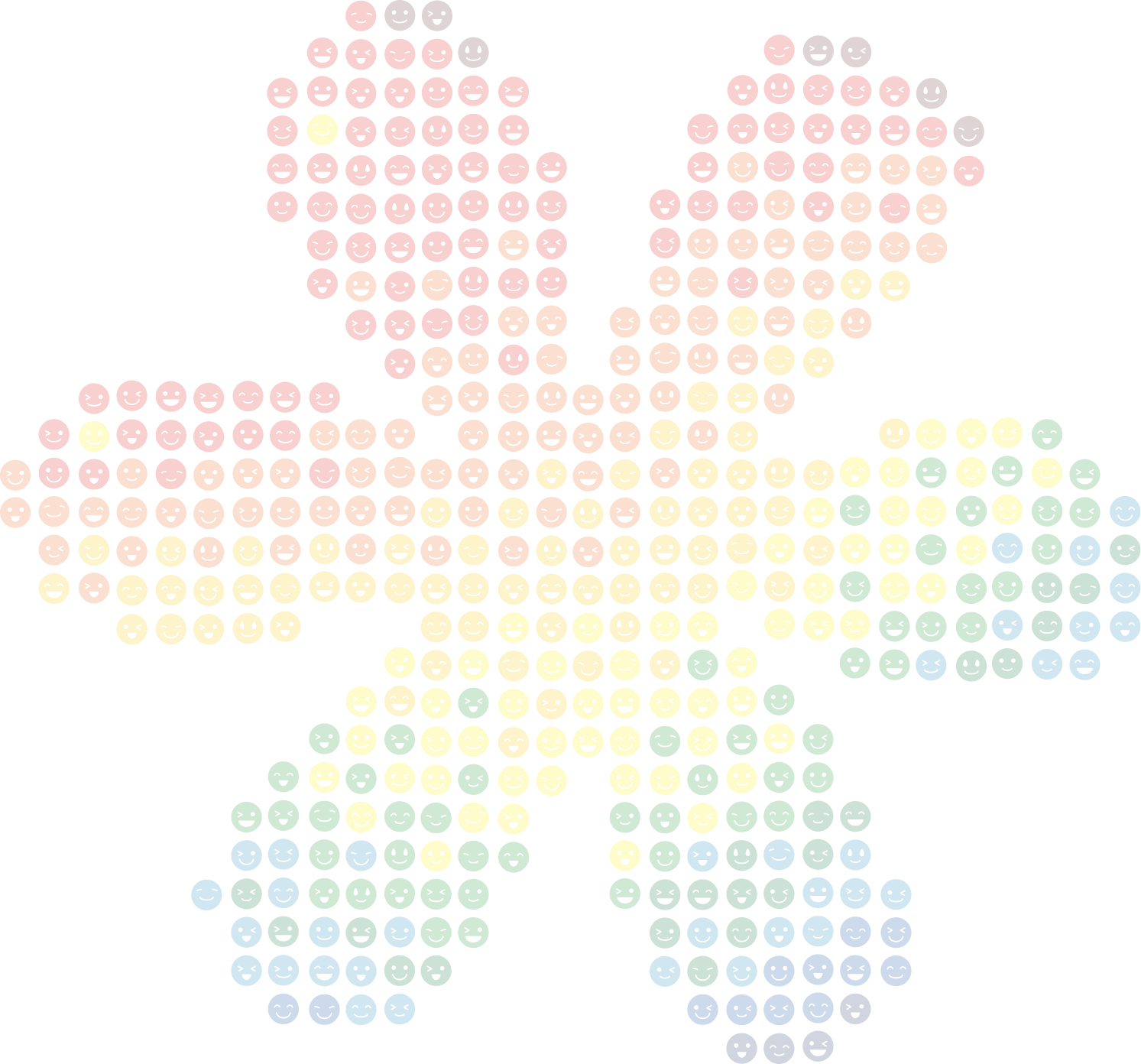社長日誌
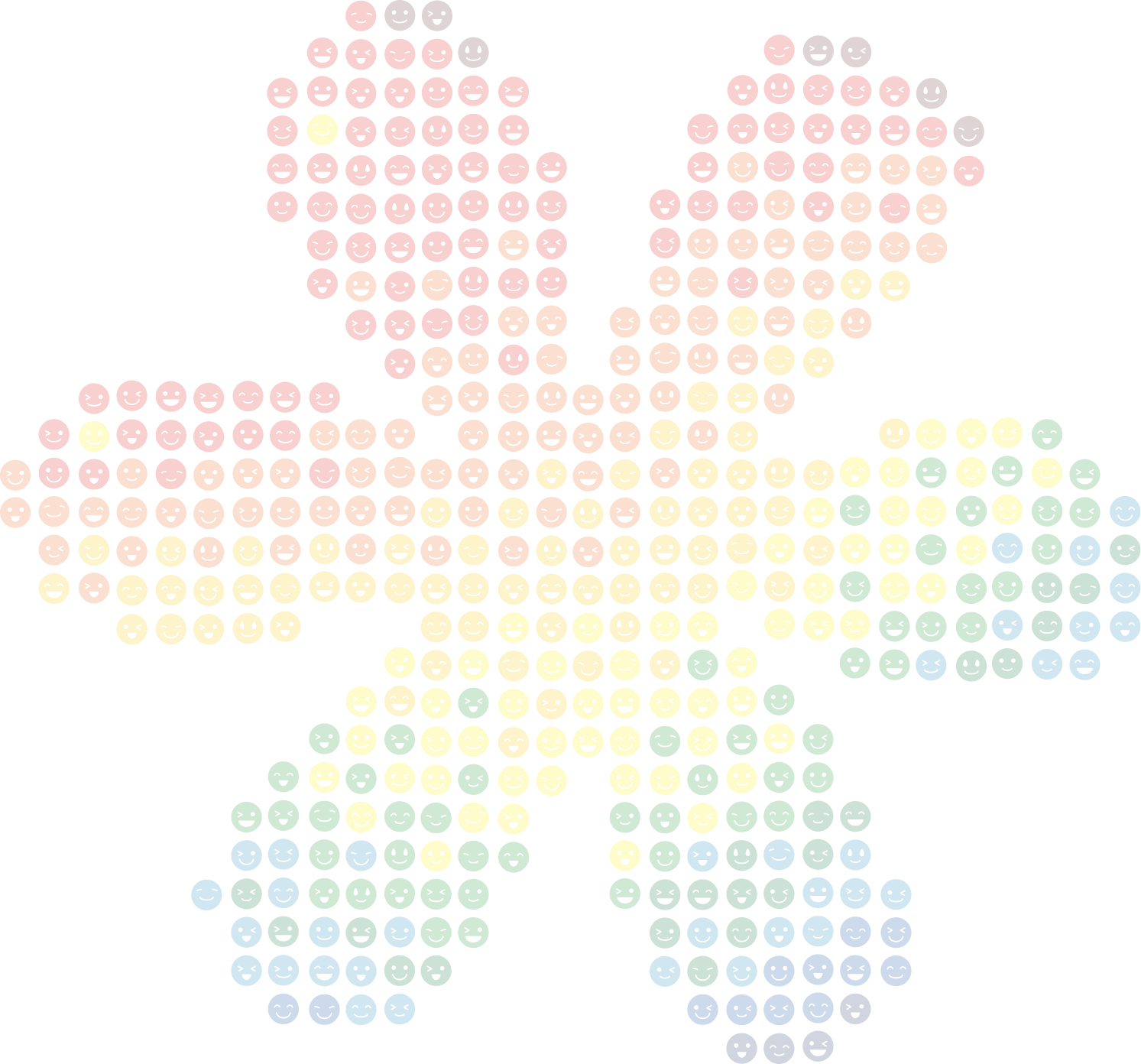
115日
昨日、中国語のレッスンの時に先生から1年の三分の一は徳島にいないんじゃないかと言われて、そんな多くはないだろうと、今年の手帳で数えてみました。
まだ、1年は終わっておりませんが、12月末までに決まっている出張も含めると、115日間、出張しております。
約31.5%なので、ほぼ三分の一といっても間違いありません。
自分ではそんなに出ている気はないんですが、数えてみると結構、出ているもんなんですね。(^^;)
タムラ味噌二郎
本日の昼食は北島町のタムラで食べました。
今回、注文したのは11月末までの限定メニュー「タムラ味噌二郎」です。
そうです。
東京三田のラーメン二郎の背脂、野菜増し、辛め、ニンニクといういメニューをカバーしているのだと思います。
もやしをスーパーのもやしパック4袋分使用しているとのことで、食べ始めは自分がラーメンを頼んだのを忘れてしまうほど、もやしばかりを食べてしまうことになります。
歌謡曲でカバーはよくあることですが、ラーメンで有名店のメニューをカバーとはあまり聞きません。
また、オリジナルの良い面を真似しつつも自店の味を出しております。
限定メニューなのも良いですね。
お昼ご飯を食べに行っても勉強になることは多いですね。(^^)
壊れちゃいました。
長年、愛用していたマイクロSDアダプターがとうとう壊れてしまいました。
ドコモ茸の形でストラップになっており、この日記を書き始めた頃、社員が買ってきてくれたものです。
手がとれ、足がとれても使い続けていたのですが、とうとうアダプタ自体が分解してきて使えなくなってしまいました。
形あるものは全て壊れますが、非常に愛着もあったものが壊れるのは寂しいものですね。(T_T)
新しいパソコン
先日、会社のパソコンがいつの間にか部署で一番、低スペックであることを指摘され、業務にも影響がありそうなので、買い換えることにしました。
自分が長年使っていると、毎日のように使っておりますので、いつも変わらず快適に使っているように思っておりましたが、新しいパソコンを使ってみると、色々なソフトの速度が全く違うのに驚いてしまいます。
特に劇的に違いが分かるのはフェイスブックです。
これまではフェイスブック側が遅いのだろうと思っておりましたが、何のことはない、自分のパソコンの処理能力がフェイスブックの求めるスペックに対して著しく低かっただけのことでした。
しかし、一度早く動くのが判ってしまうと、古いままの自宅のパソコンでフェイスブックを見るのが苦痛で仕方なくなってしまいました。
やっぱり人間って一度、贅沢を憶えてしまうと駄目になると言いますが、本当のことですよね。(^_^;)
フルーツマッコリ
超布屋
たこ焼き
本日は5時に自宅を出て、富山まで行き、とんぼ返りで大阪まで帰ってきて宿泊しております。
帰りのサンダーバードの中で、ます寿司とぶり寿司のセットを食べましたが、足りなかったので、大阪に着いてからたこ焼きを食べに出ました。
えびすというたこ焼き屋さんで、たこ焼き20個600円ですが、塩たこ焼きとネギ大盛りたこ焼きを20個ずつ、こもだ布団店の菰田さんと一緒に食べました。
最初は塩だけにするつもりだったのですが、塩を食べ始めたら止まらなくなり、結局、ネギ大盛りも追加で頼んでしまったのです。
まあ、両方とも絶品で、やっぱりたこ焼きは大阪だよね。とか言いながら、食べたんで食べ過ぎても後悔はないんですけどね・・・ 多分(^^;)
オサキ婚活する
2010年に「このミステリーがすごい」大賞隠し玉となった「もののけ本所深川事件帖 オサキ江戸へ」の第3弾です。
このての作品は読み物としては面白いのですが、元々私は歴史が好きなので、作中の内容がどの程度、事実を下敷きにしているのかが、いつも気になってなりません。
この作品では、疱瘡地蔵なるものがあり、これが現在のNHK大河ドラマの主人公「お江」と深い関わりがあるということが話の骨子になっており、いくつかのエピソードもまことしやかに織り込まれております
しかし、これらが全くの創作なのか、事実を下敷きに創作しているのか、事実を書いているのかが気になって仕方がありません。
本日、インターネットで調べても疱瘡地蔵なるものは出てきませんし、こんなに気になる人はこの手の本を読むのは向いていないのかもしれませんね。(^_^;)
シドロ
クレーンゲーム