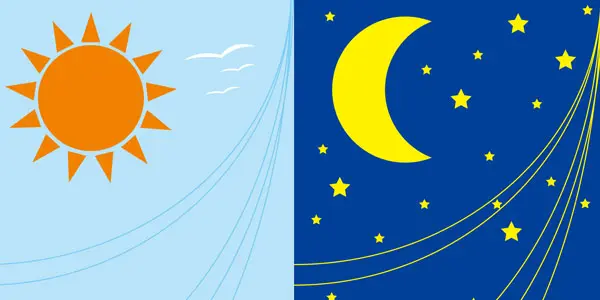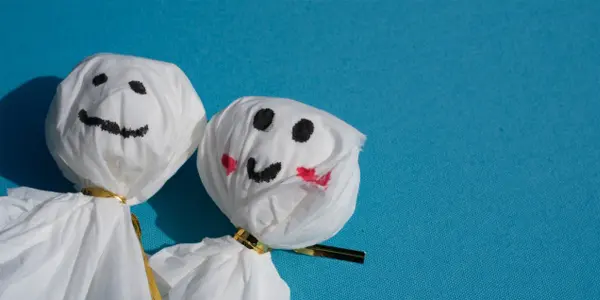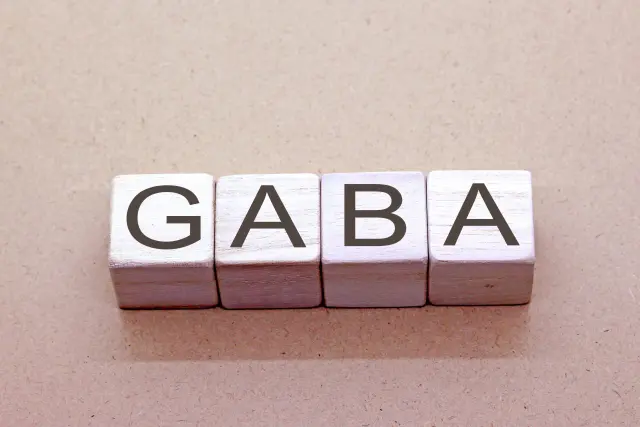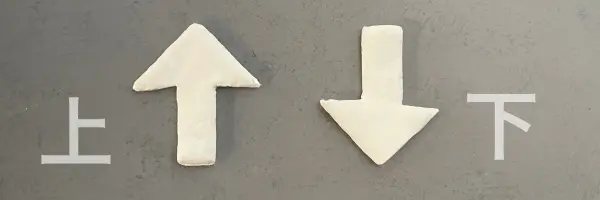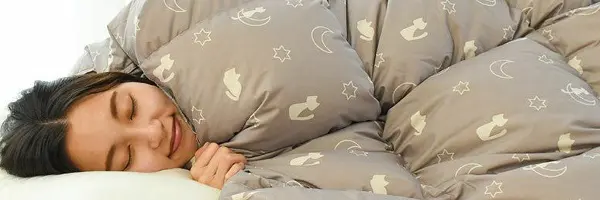さて、今回は・・・、
「梅雨時の快眠ガイド:湿気対策で寝苦しさを解消しよう♪」
について、ご紹介します。
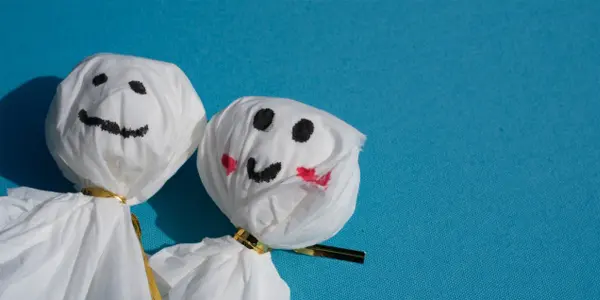
梅雨の季節は雨が続いてなんだかじめじめしちゃいますね。
そんな雨の日。
雨のおかげであんまり気温は高くないのになんだか寝苦しいな……と感じたり、
室温は快適な温度にしているのになぜか眠りが浅いな……となったり、そういう時はありませんか?
それ『湿気』や『湿度』が原因かも!
梅雨時期は特に雨が続くせいで布団もなんとなく湿気てしまいます。
そのせいで寝苦しさを感じる可能性、ありです……!
今回はそんな梅雨時期をはじめ、湿度対策としての『除湿』を中心にご紹介していきます!
■ 湿度が睡眠に与える影響とは?

湿気や湿度が睡眠にどんな風に影響を与えているか、という話から始めましょう。
皆様は「寝床内気象」もしくは「寝床内気候」という言葉をご存知ですか?
「しんしょうないきしょう(きこう)」と読み、漢字の意味の通り、「お布団の中の気温・湿度」のことを指します。
一般的に人間が眠りやすい布団の中の気温は「32~34℃」。湿度は「50%」が理想と言われています。
布団の中の温度は、暑い寒いといった感覚として感じやすいので調整がしやすいのですが、実は湿度は極端に湿気ていたり乾燥していないかぎりは分かりづらいもの。
室温も最適、布団もいい感じ、と思っても「なんか寝づらい」「なんか眠りが浅い」となる場合は「湿度」が高すぎる・低すぎることが原因の可能性があります。
例えば、冬の寒い日にしっかり布団を着込んだはずなのに蹴飛ばしてしまっている。
例えば、クーラーをかけて涼しくしてから寝たのに汗がじっとりとまとわりついてきて気持ち悪くて目が覚めた。
……なんていう時は布団内の湿気による「蒸れ」のせい、なんてことも考えられるのです。
分かりづらいからこそ見落としがちな「湿度」。心当たりがある方は是非、湿度を気にしてみてください!
■ 対策その1、布団を「乾燥」させよ!

じゃあ具体的にどうしたら湿度を50%ぐらいにできるのか。
という時に、まずは布団本体の「湿気」を追い払うことを考えてみましょう!
人間は寝ている時にコップ1杯分の汗をかきます。そのかいた汗は、多くはパジャマが吸ってくれるのですが、まくらや敷布団、掛け布団も汗をすってくれます。
寝具が湿り気を帯びていると、水分が飽和してしまい、寝床内の湿度は上がってしまいます。
なのでまずは寝具をさっぱり!乾燥!させることが大事!
起きたら掛け布団はあげておく、最低でも1週間に1度は敷き布団やマットレスを持ち上げて立てかけて空気を通して乾燥させる。
それだけでも充分な効果が期待できます!
でも雨続きで干せない、そもそも干すのが面倒……という方には、除湿シートや布団乾燥機を使うのもあり!
除湿シートはマットレスの下に敷くことで湿気を吸ってくれる便利なシート!薄手で扱いやすいので干すのも難しくはないのが嬉しいポイントです。
布団乾燥機もうまく利用して、湿気を飛ばす方法もおすすめです。
■ 対策その2、布団の「機能」を確認せよ!

布団はしっかり乾燥させてはいるよ!でも寝苦しいよ!
という方は、使っている布団の機能をチェック。
通気性の良い布団を使っていますか?
綿や麻など、天然繊維でできている布団は吸湿性がよく、汗をたっぷり吸収してくれます。
また通気性が良いものも多く、中に空気がこもりにくいので蒸れにくい素材になっているのです!
ほかにも羽毛は調湿機能を備えており、冬場だけでなく夏場にも活躍するお布団。
夏は「ダウンケット」「羽毛肌掛け布団」といった名前で調べてみてください!
ポリエステルをはじめとする化学繊維も吸湿性は天然繊維程ないものが多いのですが、さらっとした触り心地が続くのでお好みに合わせてお使いください!
■ まとめ

いかがだったでしょうか?
湿気と上手く付き合うことで今よりもより眠りやすくなる可能性があります。
なんだか眠りづらいな、と思った時は「もしかして湿気かも?」ということで対策をしてみてください!
また過去のブログで参考になりそうな記事もご紹介!
具体的にどれぐらいの気候でどういうお布団を選ぶのがいいの?が知りたい方はこちら ↓
季節に適した寝具の選び方
ここまでお読みいただきありがとうございました!