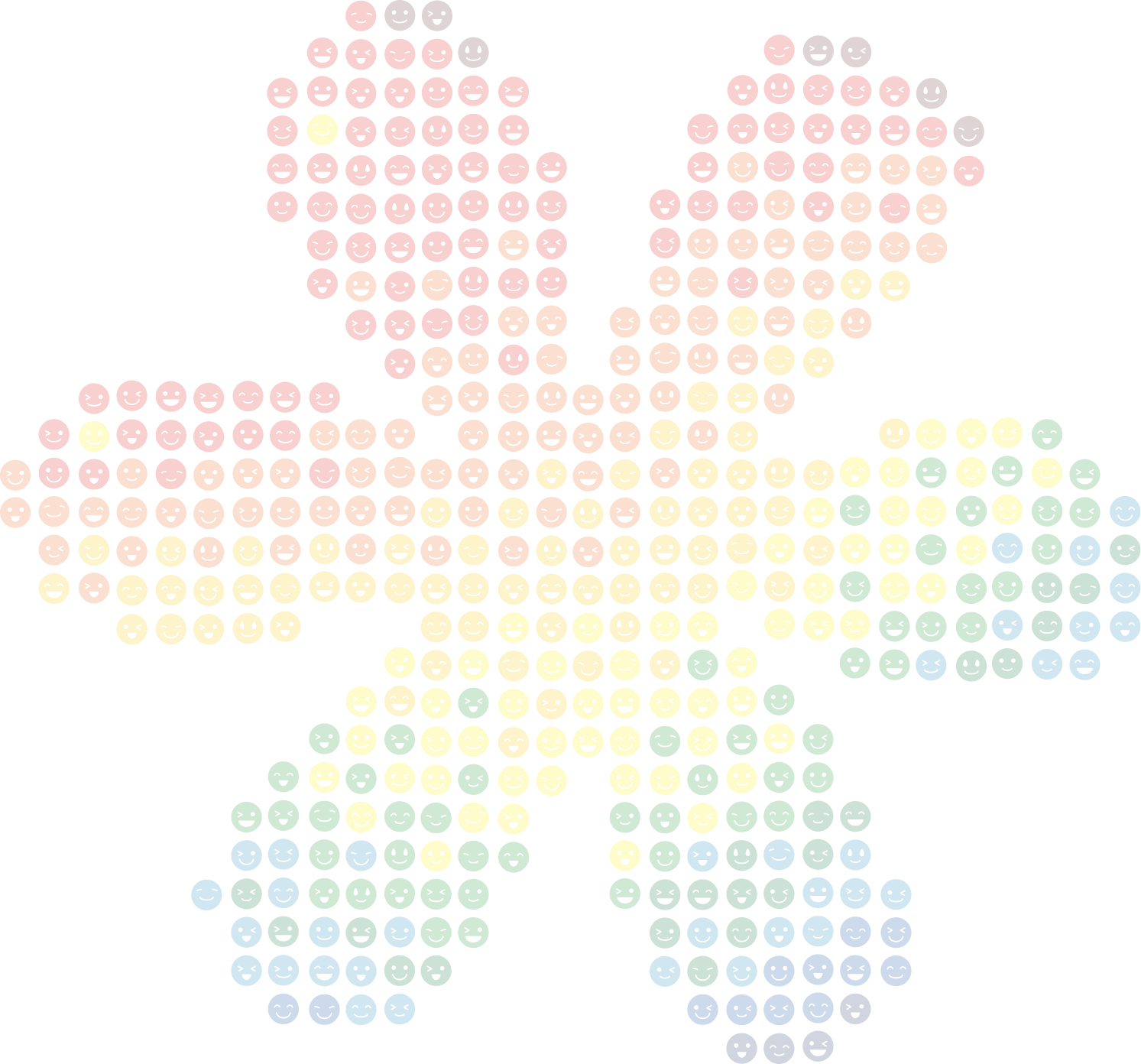社長日誌
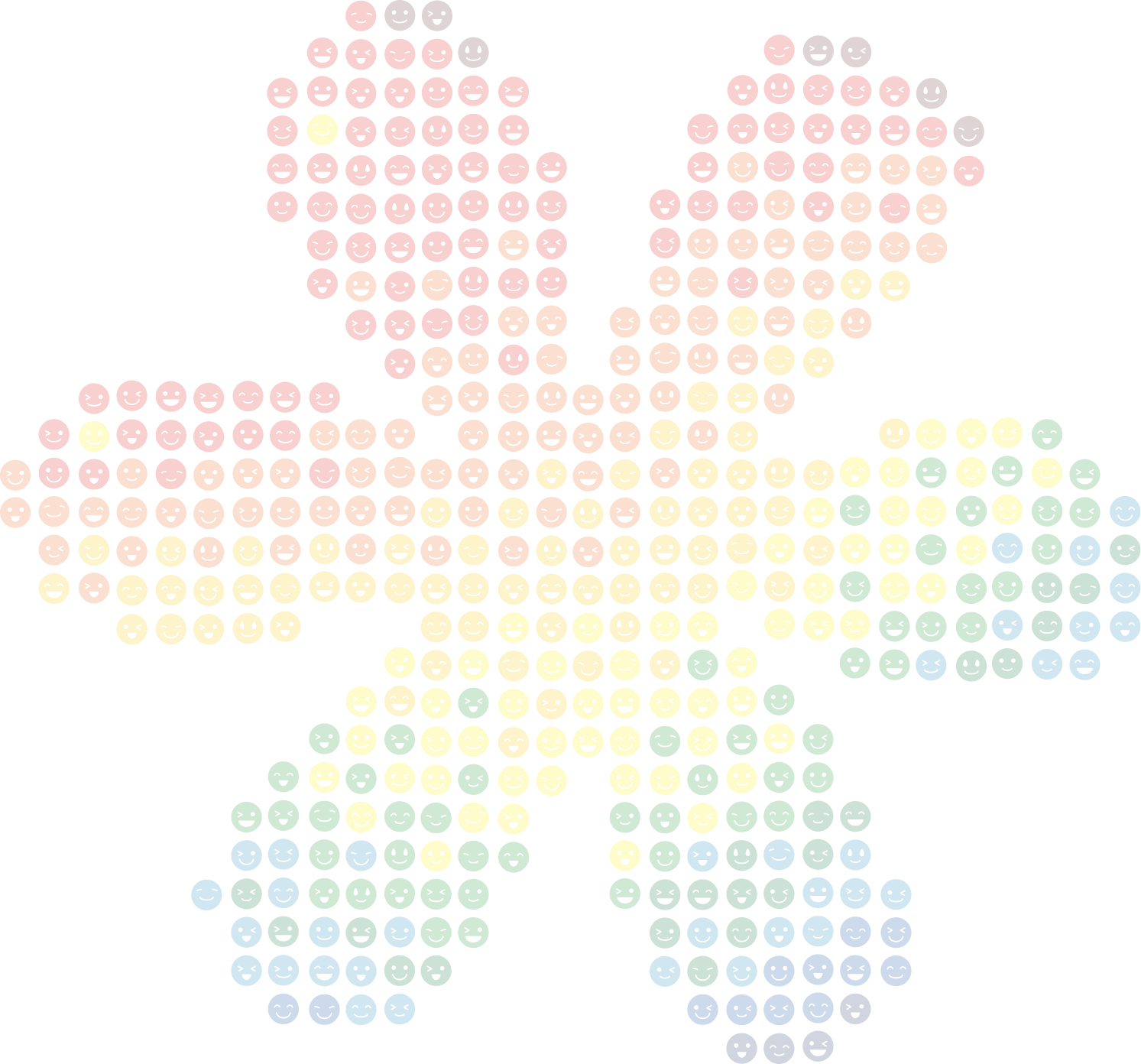
ライトアーム
本日は中小企業家同友会の北支部準備会10月例会でした。
報告者は岡山同友会にお願いして、有限会社ライトアームの林明美社長にお越しいただきました。
林社長は12年前に社員から社長になって十数年社長として経営にあたってこられておりますが、「とことん社員と関わって」という報告テーマのように社員一人一人と関わった経営に邁進されております。
今回は女性経営者の報告ということで徳島同友会の女性経営者の方も多く参加されておりましたが、女性経営者の方だけではなく多くの男性経営者も感銘を受けられたと思います。
私自身も多くの学びを得ることができて、感謝です。(^^)
水没
今朝、当社がオーダー枕を屋台販売しているショッピングセンターが水没しているという連絡がありました。
担当者は店に入ることができずに、本部へ来ておりましたが、どうやら床上70㎝くらい水が入っているようです。
今年は台風が続いてきたので、予想外に水が出たのでしょう。
しかし、商品も屋台も泥だらけだと思いますので、商品はもう駄目だと思いますが、屋台を洗えば大丈夫かどうかが心配です。
復旧もスピードが重要ですので、明日からまた忙しくなりそうです。(^^;)
社内報告
本日は店長会でしたので、先月の通販事業部店長に続き、管理本部長に報告をしてもらいました。
当社では先月に報告した社員が次の報告者の座長になると決めてあるので、2回ほど2人でプレ報告をした後、本日の本番に臨んだようです。
管理本部長は取引先の専務だったのですが、その会社が倒産した際に当社へ入社していただいたのですが、その会社でバリバリ働いた20代のことや会社が倒産する際に非常に辛かったこと、また、当社に入社して良かったということなどを話してくれました。
私自身も取引先の専務時代から親しくお付き合いさせていただいていましたので、知っていることもありましたが、飛び飛びに知っていたことが一つの流れとして理解でき、本部長のことをより理解できると同時に本当に入社してもらって良かったなあとあらためて思いました。
自分自身を振り返り報告するということは、それまでの自分の人生でどこにどのようなきっかけがあったのかというようなことを気付くきっかけにもなりますし、周囲もその人の人生にふれることで、報告者に好感を持つようになりますので、本当に良いことだと思います。
今後も継続していくことになると思いますが、これからも楽しみです。(^^)
昇級
本日は休日でしたが、早朝から長男の弓道の昇級試験があるということで鳴門まで送らされました。
更に15時くらいに迎えに来いということです。
せっかくの休みがつぶれてしまうので、少しブルーな気分になっていましたが、迎えに行くと長男が弓を持って飛び跳ねながらやってきます。
昇級試験に受かって余程嬉しかったのでしょう。
まあ、こんなに嬉しいなら迎えに来た甲斐もあるものです。
また、長男を迎えに来るついでに次男と行った鳴門の海岸では、ここしばらく海が荒れているせいか色々な貝を拾えることができて、大漁です。
充実した1日と言えるかもしれませんね。(^^)
↓タカラガイ22個、マクラガイ49個他、バイガイ、スダレガイ、チリボタンなどなどです。
大雨晴れ大雨
昨日、帰国したばかりですが、本日は大雨にもかかわらず、和歌山へ出張です。
今回は日帰りだったので、行きも帰りも淡路島で、大変で面白い(?)体験ができました。
数十㎞走るごとに天気と雨が繰り返すのです。
やはり台風なので、雲が渦状に巻いており、その切れ目が晴れているのですが、その差が激しくて前の見えないような大雨を抜けると、晴れてきて、しばらく行くとまた大雨というふうなかんじでした。
昨日からの大雨で鳴門から志度の間が通行止めになっていて、私は関係ありませんでしたが、帰りに松山行きの定期バスが鳴門でおろされていたのを見て、このバスは何時に松山に着くんだろうと気の毒に思いましたね。(^^;)
第三者検品
昨日は午後から検品会社に行っておりました。
中国での検品は大きく、商品を作った工場でする工場検品と工場とは全く関係のない検品専門の検品会社で検品する第三者検品に分かれます。
先日、当社に入荷した商品に運送上の不具合があったため、物流のどこに問題点があったのかを調べることと、しばらく検品会社を見学していなかったので、勉強も兼ねて本日の訪問となりました。
本日訪問した会社は日系の企業でアパレル、寝装品、雑貨の3部門を中心に170名ほどのスタッフで運営しているとのことです。
会議後に現場を見学させていただきましたが、検品場で熱心に1枚1枚検品しているのを見ると、本当に大変な作業だということが判ります。
お客様に良い商品をお届けするためには重要な行程ですので、今後も頑張ってほしいものですね。(^^)
上海経済セミナー
ウコンの力
本日は上海に来ております。
夕食は20人ほどで中華ですが、予想通り乾杯(一気)の連続になってしまいました。
最初はビールだったので可愛いものだったのですが、そのうちに紹興酒、白酒とエスカレートしてベロベロになってしまいました。
つぶれていた人もいたようですが、自分のことで精一杯でよくわかりませんでしたが、あとで自分が撮った写真をみると結構酷そうです。
写真は修羅場なので、公開は控えさせていただきます。
しかし、関西空港で、せっかく買ったウコンの力を飲み忘れたのは痛恨でした。(^^;)
知っておきたい我が家の宗教
中秋の名月